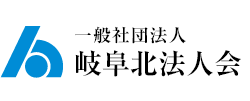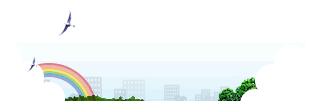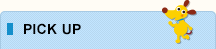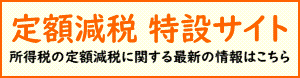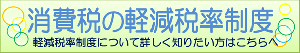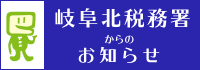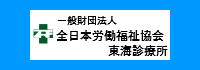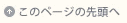ふるさと秘話 No.87
ゾルゲ事件の県人たち
エッセイスト 道下 淳
このほど久しぶりに出会った友人と、お茶を飲みながら長話をした。話題は先の戦争中に検挙された国際スパイ団「ゾルゲ事件」についてだった。その中心人物のひとり尾崎秀実(ほずみ)氏は刑死(1944)した。父親は、加茂郡白川町の出身だった。それだけにこの事件の関係者には、岐阜県出身者も多かった。それに筆者は岐阜市北長森にあった引き揚げ者寮に入居しておられた秀実氏の父親を訪ねたことがある。そんな話をしているうちに、時間が過ぎてしまった。筆者はこのとき引き揚げ者寮の前身、中部4部隊(歩兵68連隊留守隊)のことを思い出した。
引き揚げ者寮に尾崎秀実の父秀真(ほずま)氏を訪ねたとき、旧兵舎の内務班(分隊)をそっくりベニヤ板で仕切り、1世帯ずつ入室者に割り当てていた。兵舎時代は廊下側に鉄砲を置く銃架があった。それが敗戦により、民間に解放され、感慨無量だった。
筆者が中部4部隊の第7中隊1班に入ったのは、昭和19年(1944)10月のこと。入隊当日はお客様扱いだったが、翌日から待遇が一変し、ひどい仕打だった。同期の兵隊は約1,000人いたが、半月ほどたった真夜中にたたき起こされ、新品の軍服に竹の水筒を持ちひっそり出発した。もちろん見送りは許されなかった。このなかに2人の友人がいたが戦死した。戦後に調べたらこの部隊は、中国南部で戦ったそうである。
ところで尾崎氏ときみ夫人が入寮した部屋であるが、広さ20畳ほどで、床は軍隊当時の板張りのままであった。隣りとの境の壁には、ベニヤ板で片開きの扉をつけた整理棚が8個ほど造り付けられ、ふとん、衣類、身回り品から食器類まで収納していた。片隅に木造のベッドがあった。筆者らは鉄製のベッドを使用したが、それらは全部木造と換えられたらしい。入居する時ベッドは買ったそうだ。
尾崎夫妻はだだっ広い感じの板の間中央に、4枚ほどのムシロを敷いて座っておられた。よく見るとムシロは畳代わりの上物でなく、穀物などを入れるカマスを解いたものであった。炊事は廊下にコンロを置いて行ったが、水を運ぶのが大変と言っておられた。
夫人は岐阜市内の繊維工場へ通い、わずかな労賃で一家を支えておられた。フロは軍隊時代からの「六八湯」があるものの、生活のことを考えると、たまにしか行けないと、笑われた。
尾崎家へ取材に行くとき、手みやげになにか食材になるものをと、上司からなにがしかのお金をいただいた。古いことなので、全額は覚えていない。早速駅前のハルピン街でヤミのメリケン粉(小麦粉)を1斤(600グラム)か2斤、買って出かけた。上司も同家の家計の苦しいことを、知っていたからであろう。この手みやげにきみ夫人はよほどうれしかたとみえ、何度もお礼を言われた。
2回目にはやはりハルピン街でヤミで売られているジャガ芋を求めた。手みやげにジャガ芋を選んだのは、次の理由があったためである。同居人に末子で中学のスエ子さんがいた。学校では給食が出るが、遠足のときは各家庭でおにぎりとかいなりずしなどを用意した。ところが尾崎家では当日弁当にするような食材がなく、きみ夫人はうでたジャガ芋に食塩を添え、弁当代りにした。スエ子さんは何も言わなかった。母親に悲しい思いを、させたくないためではなかったろうか。この話は前回訪問したとき、夫人から聞いた。末子さんの兄で上京していた秀樹(ほずき)氏の初期の作品で、ゾルゲ事件に関する自伝的な「生きているユダ ―ゾルゲ事件― その戦後への証言」のなかでもこのことが思いを込めて記されている。
ある日、引き揚げ者寮でばったり、病身らしい秀樹氏に会ったことがある。3回目か4回目の訪問のときである。早速初対面のあいさつをした。東京の新聞社に勤めているが、胸が悪いため人並みの活動が出来ない。兄秀実氏の友人が、何かと親切にしてくれると語られた。そのなかで、川合貞吉氏(大垣市出身)や伊藤律氏(瑞浪市出身)らの名前が出た。うち伊藤氏は戦後米陸軍省が発表したゾルゲ事件の報告のなかで取調べのとき、同志の名前をもらし、それが事件発覚の糸口になったとされる。当時は秀樹氏もこの情報を知らなかったとみえ、伊藤氏に対し、さほど批判がましい発言は聞かれなかった。
川合氏はやはりゾルゲ事件に連座し、10年の刑を受けた。しかし戦後の政治犯釈放で出獄した。秀実氏らゾルゲ事件関係の話をよく聞かしてもらったと、秀樹氏は語った。「生きているユダ」にも川合・秀樹両氏が同じ寮に住んだことがあり、川合氏の語る事件に関係した同志の話は『たしかに生きていた。川合の愛情のこもった言葉のなかで、かれらは躍動していた』と、記している。また『秀実のことを語るとき、川合の言葉は力点をつけたようにひびく』とか、『尾崎以上に愛情の豊かな人間はざらにはいません。その愛情があったからこそ、私は励まされ導かれて最後まで闘えたのです』と、印象的な文章で結ばれている。
秀樹氏が上京するとき頼ったのは、東京・目黒に住んでいた秀実氏夫人の英子さんだった。しかし期待したほどのめんどうは見てもらえなかった。そのため職と住を転々とし、苦労したわけである。長女の楊子さんは戦争中岐阜に移り、しばらく加納高等女学校に通っていた。学校でも父のことが気になるのか、ひとりぼっちでいることが多かった。と、かつてのクラスメートから聞いたことがある。秀実氏が獄中から英子さんや楊子さんに宛てた書簡を集めた「愛情はふる星のごとく」は、戦後ベストセラーになった。このなかには子を思う秀実氏の気持ちがあふれ、涙無しには読めない。
秀樹氏が追及していた伊藤氏は公職追放の際、身を隠し中国に渡った。同55年(1980)帰国したがゾルゲ事件などについて何も語らぬまま、平成元年8月に、また同事件を追及していた秀樹氏は同11年9月、それぞれ死去された。秀樹氏は、61歳の働き盛り。大衆文学研究に大きな足跡を残されただけに、その訃報は悲しかった。

旧歩兵68連隊で、中央の2階建てが6・7中隊だった。引き揚者寮は左、平屋建て物の辺りにあった。(昭和30年代中ごろ写す)